令和の飢饉にどう向き合うのか?
はじめに
遠野物語を読み思ったことがあります。
もしかして現代は大飢饉なのでは?と、
この記事では、遠野物語を読み解いた先にある、当時の時代背景を現代に投影し比較していきたいと思います。その上で、どのように生きていけばよいのかを考察したいと思います。
私は文学者でも社会学者のような専門家ではないので、あくまでも一読者が「遠野物語」を読み、実際に遠野に赴いた際の感想と考察を述べています。

遠野物語とは?
『遠野物語』(とおのものがたり)は、柳田国男が明治43年(1910年)に発表した、岩手県遠野地方に伝わる逸話、伝承などを記した説話集である。
遠野地方の土淵村出身の民話蒐集家であり小説家でもあった佐々木喜善より語られた、遠野地方に伝わる伝承を柳田が筆記・編纂する形で出版され、『後狩詞記』(1909年)、『石神問答』(1910年)とならぶ柳田の初期三部作の一作。日本の民俗学の先駆けとも称される作品である。(ウィキペディアより)
序文には「願わくはこれを語りて平地人を戦慄せしめよ」という言葉があります。「平地人」とは町や暮らしで文明的な暮らしをするいわゆる豊かな人々です。
どんな話?
土地の人に語り継がれた、遠野の不思議な話を集めたものです。
不思議な物の中には、「河童」や「座敷わらし」といった妖怪について多く語られています。その真意は遠野にある「伝承館」の展示や昔話で知ることができると思います。
本当は怖い「遠野物語」
遠野物語における「河童」とは?
正体はズバリ「人間の子供」です。前近代農村では、“働ける身体”=最大の資本でした。障害を持つ子ども、病弱者、幼児や高齢者は、飢饉時には「余剰口減らし」と見られることもあった。
その存在を正当化・意味づけするために、「霊的に価値がある」「家を守る」などの物語が生まれた可能性があります。

遠野物語における「座敷わらし」とは?
本当は労働力にならない存在(幼児・障害児)を「家を守る神」として位置づけ、共同体に受け入れさせる。
農民に対して、裕福な家=長者は労働力にならない存在でも食べさせることができました。しかしながら、農民は口減らしをしているため表には出せない。農民は偉い人=長者を直接批判することができない。このような状況で「座敷わらしがいるとその家は栄える」という言葉に言い換えて伝えてきたのだと思います。
生存論理
飢饉のたびに「誰を生かし、誰を切り捨てるか」が問われた農村社会。
その現実を露骨に語るのは残酷すぎるため、「かっぱにさらわれた」「座敷わらしになった」という物語で包んだ。つまり民話は、生存のためにやむを得ず行った行為を、共同体で受け入れるための言語化であったのではないかと思います。
この状況は農村では毎年のように、「誰が生き残り、誰が生き残れないか?」という命の選択が行われていたということになります。
もう一つの遠野の物語
遠野には「伝寺野」という地域があります。この地域は60歳を超えた老人が共同生活を送ったとされる場所です。いわゆる一種の「姥捨て伝承」ですが、完全な棄民ではなく、草鞋作りや子守りなどの軽労働で生き延びた痕跡が伝わっています。つまり「村が養えないが完全には見捨てない」という折衷的な制度といえます。
ただし、一度「伝寺野」へ渡った親と農地であっても口を聞いてはならないという厳しい掟もあったそうです。
これらの話をもとに当時どのような状況であったか?
• 飢饉や冷害 → 食べ物=生命線。
• 農民は「誰を生かし、誰を減らすか」を迫られる。
現代はどういう時代か?
• 貨幣経済においては「可処分所得=生存資源」。
• 高負担(税・社会保険料・教育費)=現代版の飢饉。
• 家計を守るために「子どもを産まない/減らす」という選択が広がる。
これは制度的に認められた「合法的な口減らし」と言える。
日本は“飽食”でも、貨幣を得られない人には食は届かない。つまり「食料危機」ではなく「購買力危機」が飢饉を形を変えて再現している。
しかも格差拡大により「余剰人口」とされる層が増え、再び“口減らし”に似た現象(少子化・非正規雇用)が進んでいる。
飢饉と現代社会の相似
• 昔の飢饉:冷害や凶作+年貢負担で「食」が不足。
• 現代の飢饉:高負担(税・年金・医療・介護費)+実質賃金の低下で「可処分所得=生存資源」が不足。
→ どちらも「自分の意思では抗えない圧力」が生活を締め付ける。
ではどう生きていくのか?
柳田国男と同じ時代で、遠野物語の舞台でもある岩手県花巻出身の作家で宮沢賢治がいます。
彼は、岩手県をイーハトーフ(理想郷)と位置づけています。
遠野物語では、「人間の理解を超えた世界が日常と地続きにある場所」と描かれ、宮沢賢治は「「人と自然が共に生きる理想郷」と描いています。宮沢賢治自信も岩手での冷害・飢饉・農村の貧困を目の当たりにしています。
ここに現代の厳しい世の中を生き抜くヒントがあるのではと考えます。
宮沢賢治のイーハトーフ
イーハトーブは「岩手=現実」をもとにした理想の地(精神的岩手)。
『風の又三郎』『グスコーブドリの伝記』『銀河鉄道の夜』などに共通するのは、「自然は厳しいが、それと調和する心を持てば世界は光に満ちる」という思想です。
「どこまでも透きとおるような空気と、燃えるような稲穂の波。そこに人は祈り、科学を学び、労働を愛する
宮沢の世界では、山や風や星は“怖い存在”ではなく、“語りかけてくる友”と扱っています。
アメニモマケズ
宮沢賢治の病床のなかで手帳に記したメモに、有名な「アメニモマケズ」という下りがあります。まだ全文を読んだことのない方は是非お読みください
このメモは長いメモで内容の核心としては、
1. 雨風に負けない強さ=環境に振り回されない
現代でいう「雨風」とは、SNSの炎上、情報の洪水、景気変動、これらに振り回されず、自分の軸を保つことが格差に流されない第一歩です。
2. 欲に流されず、怒りに囚われない=比較のゲームから降りる
格差社会では「隣の人との比較」に心を削られがち。
アメニモマケズは「欲を抑え、怒らない」ことで、自分自身のリズムを守ることを教えてくれます。
3. 身近な人を助ける=小さな利他の積み重ね
「東に病気の子あれば行って看病してやり…」
遠い理想を追うより、目の前の人を幸せにすること。
これが格差に打ち勝つ「人間らしい豊かさ」です。
4. 名誉や利益を求めない=静かな幸福観
大きな成功や目立つ立場を得ることが幸せではありません。
「そういうものに私はなりたい」とは、見返りを求めずに人の役に立つ生き方。
これは格差社会の「勝ち負けゲーム」を降りるための哲学です。
100年近く前の作家が現代の飢饉に接する人たちへ送るメッセージはとても参考になるのではないかと思います。
まとめ
今回読み進んだ内容は、「河童」や「座敷わらし」でしたが、「遠野物語」では他にも様々な不思議な話が語られています。
それら一つ一つに、背景となるもう一つの物語が潜んでいると思います。
そのような物語を読み解いていくのも読書の楽しみかと思います。
※本記事にはプロモーションが含まれています。
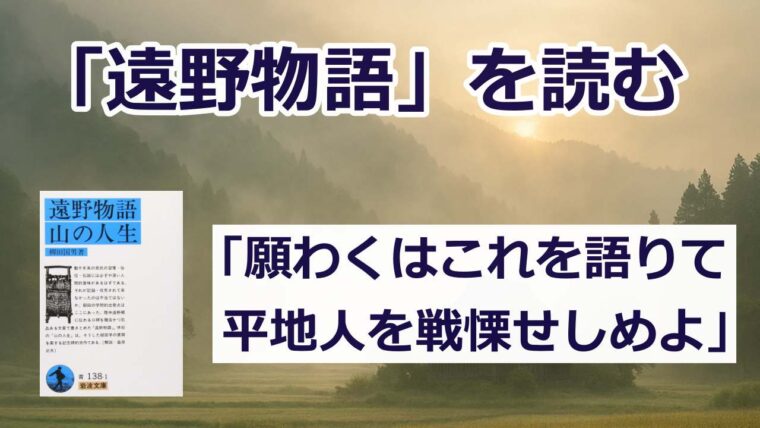
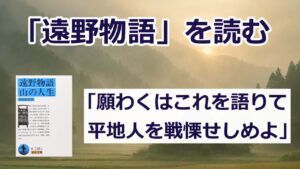
コメント